2015/10/5
贋札を手にしたら:セサル・アイラ『バラモ』
日本ではロベルト・ボラーニョの小説の翻訳が進行中だが、英語圏では、すでに詩集やエッセイ等を含めたそれが終わり、今では、アルゼンチンの作家、セサル・アイラ(1949−)の翻訳紹介に向かっているように思える。カルロス・フエンテスが早くから注目し、2020年のメキシコを舞台に、大統領の椅子をめぐる政界の思惑を描いた近未来小説『鷲の椅子』(2002)の中では「セサル・アイラはノーベル文学賞を受賞する最初のアルゼンチン人です」と登場人物の一人に言わせ、ボラーニョは『余談として』(2004)所収の「途方もないセサル・アイラ」という短文で次のように評している。
現在、ありとあらゆる分類を超える作家がいるとするなら、それはセサル・アイラである。(略)アイラは少なくとも年に二冊の本を書くという話だが、その本は、ときおり、ボルヘスの『アレフ』の登場人物と同じベアトリス・ビテルボという名のアルゼンチンの小さな出版社が出版する。わたしが入手しえた彼の作品はモンダドリとアルゼンチンのトゥスケッツ社から出ている。それが残念でならない。なぜなら、一度アイラを読めば、誰でも読み続けたくなるからだ。彼の小説はゴンブローヴィッチの理論の舞台化のように思えるが、根本的な一つの違いがある。つまりそのポーランド人は想像上の豪華な修道院の修道院長であるのに対して、アイラは御言葉の跣足修道女会の尼僧、もしくは修練女であるということ。ときにはルーセル(赤い水槽にひざまずくルーセル)を思い出させるが、彼と比較しうる現在の作家はバルセローナ人のエンリケ・ビラ=マタスだけだろう。/アイラは奇人だが、スペイン語で書く今日の優れた三、四人の作家のうちの一人でもある。

『わたしの物語』
セサル・アイラ 著/柳原孝敦 訳
松籟社刊、紹介ページはこちらへ
このように作家の好奇心をもそそる作家なのだが、奇妙なことに、これまで文学賞は1つも受賞したことがない。作品数が多く、そのほとんどが原文100ページほどで、短篇というには長く、長篇というには短かすぎる。案外、そんなところに原因があるのかもしれない。そんなアイラの作品についてはこれまでいくつか紹介してきたし、すでに『あたしが尼僧になった理由(わけ)』(邦題『わたしの話』、松籟社)が出ているし、まもなく『文学会議』も出るはず。それでも、ここでは『バラモ』(2002)を通して、アイラの別の面を見てみたい。この作品は次のように始まる。
一九二三年のある日、パナマのコロン市で、三等書記官が一日の仕事を終え、月の最後の平日であったため給料を受け取りに会計に立ち寄ったあと、勤めている庁舎から出てきた。その瞬間から翌日の夜明けまでという時間の間に、つまりおよそ十時間から十二時間後に、彼は長篇の詩を、書くと決めてから最後のピリオドを打ち、その後は補足も修正もしないような詩を書き上げた。その時間帯がこのとき限りのものであるとするには、彼は半世紀の人生で、それまで一度として一つの詩さえ書いたためしがなく、そんな気になったこともなかったし、またその後は二度と書かなかった、と言っておかねばならない。時と彼の経歴における、前例も続きもない一つの泡だった。インスピレーションは行動の中に、そして行動はインスピレーションの中にあって、たがいに育み合い消耗し合ったため、まったく何も残らなかった。たとえそうでも、その主人公がバラモでなかったなら、そして結果として生まれた詩が『幼子讃歌』という中央アメリカ近代詩の名立たる傑作でなければ、このエピソードは個人的な秘密のものとなっていただろう。(中略)エピソードには終わり(詩のテキスト)があるように、結果と呼応する原因、あるいはその逆のように、とても対称的な始まりもある。その始まりというのは、すでに述べたが、バラモがオフィスでの勤務時間を終えて給料を受け取りに会計課に立ち寄ったときにある。そして始まりを、まだ形も名もないものの始まりを、この平凡な手続きにあるとするのは、そのとき贋の二百ペソで支払われたからだった(総額二百ペソ。彼は百ペソの贋札を二枚もらった)。

『バラモ』原書
Varamo
(ANAGRAMA, 2002)
当然のことながら、この後、読者は、受けとった2枚の贋札をバラモはどうするのか、ひと晩のうちにどうやって文学史に残る詩を書き上げるのかといった2つの疑問を抱きつつ、アイラがどのような筋立てでこの疑問に答えるのか、それを楽しみに本を読んでいくことになる。それはそれで構わないのだが、細かいことが気になる読者であればさらに別の疑問を抱くかもしれない。1923年のパナマ、そして贋札という設定そのものに対して。パナマは1903年、コロンビアから分離独立。1914年に大西洋側のコロン市と太平洋側のパナマ市を結ぶ運河がアメリカの資金で開通し、アメリカが永久租借権を持つことになるが(その後長年にわたる両国間の交渉で、1999年に運河の主権はパナマに帰属)、運河の拡張工事は続き、完成するのは1940年。こうした年号と比べると、1923年という年には特筆されるような出来事はない。一方、通貨は1903年の独立と同時にコロンビア・ペソからバルボアに変わり、1ドル=1バルボアで固定。硬貨は作っても、紙幣は米ドルをバルボアとして流通させているはず。ただ、分離したコロンビアでは1923年に中央銀行にあたる共和国銀行が設立されている。ではこの年でもパナマではコロンビア・ペソが使われていたのか。そうだとしても、なぜ贋札はドルではなくペソなのか。悩んでいてもらちが明かない。とりあえず、フィクションなんだからと割り切って、先に進もう。
バラモは贋札の給料を受け取ったまま役所を出る。役所前の通りを歩いていると、イスパノ=スイサ社の大型車のクラクションの音に足を止められる。その公用車を運転手していたのはナンバー賭博の世話をしている黒人。バラモも、つけでその賭けをすることがあり、借金の督促かと怯えるが、彼の母親のナンバーが当たったとのこと。わずか1ペソのその儲けを受け取り、ふたたび歩き始めると、通りではインディオの女性たちが列をなして店を広げている。その一人から、さいころの形の赤いキャンディーを買い、指でつまむ。小銭がないので、先ほどもらった1ペソを出すと、お釣りがない。彼女は脚の悪い男に両替を頼む。大声を上げて両替を頼みながら長い列を進んで行ったその男はようやくのことで戻ってくると、紙幣・硬貨の発行に関する政府のやり方を長々とぼやく。「(略)役人ってのは何もせんで給料がもらえるのか。札を刷るより硬貨を作るほうが高くつくって言うなら、どしたら札を刷らなくなる? 低い額面は高い硬貨、高い額面はむちゃくちゃ安い札、そんなやり方をどうしても採用しなくちゃならんなんて、どこに書いてある? 逆だろが? 逆のほうが、もっと論理的だろ?」。彼に礼を言って支払いをすませたバラモは、指の間でべとべとになった赤いキャンディーを捨てるのに困って公園の木にくっつけた後、広場で国旗を降ろす光景を眺めて家に帰る。疲れをいやすためにベッドに横になるが、体にあたるものがあり、手で思い切り払いのけると、銀時計。それは転がって戸棚に当たって揺すぶり、買い蓄えていたインスタント食品が転がり落ちる。もう寝ることもできず、唯一の趣味である、魚の剥製作りにとりかかる。独学なのでなかなかうまくいかず、おまけに「ピアノを弾く魚」を目指しているものの、本物のピアノを見たこともない。やがて魚には腕も手も指もないことに気づき、愕然となる。そんなとき玄関のドアが閉まる大きな音にあわてて見に行くが、家の中には誰もいない。外を見ると、悪口を言われた母親が腹を立てて、隣近所に向かってわめき散らしている。バラモは何とか母親を家に入れる。彼女が夕食の支度をしている間、1人でドミノをし、給料の支払いが遅れているので貯金でやりくりしなくてはならないと言い、夕食後、近所のカフェで一時を過ごすという日課を果たすため家を出る。するといつものようにどこかから〈声〉が聞こえてくるが、それは「短い語句、定義、決まり文句、だが意味がない」。通りを歩いていくと、少し先の交差点で大型、小型2台の車が衝突するのを目撃する。被害が大きかったのは大型の方で、小型車は姿をくらます。大型を運転していたのは、彼に母親の儲け1ペソを渡したあの運転手で、中には経済大臣がいる。2人で彼を救い出し、近くの家にかつぎ込む。その夜内務大臣が突然辞職し、その役が経済大臣に回ってきたため、走行時間の正確さを競うカー・レースの視察に来ていたのだと言う。担ぎ込んだ家の持ち主は60歳代のゴンゴラ姉妹。姉妹はバラモのことを知っているが、2人は普段は家に引きこもっているためバラモの記憶ははっきりしない。彼女たちは高い関税がかけられているゴルフのクラブの密輸で生計を立てており、港に停泊している船との連絡用に無線を使って暗号を送っている。それが例の「声」の正体。バラモは口実をつけて抜け出そうとするが、その家の女中のことが気になり台所に向かう。そこにつながる部屋には密輸に使う連絡用の機器が並んでいる。やがて女中が来て、その機器がアナーキストに使われ、ハイチの侵略を容易にするかもしれない、だから暗号コードを変えてくれ、とバラモに頼む。彼はそのコード表を持って家を出てカフェに向かう……。
長々と粗筋を書いてきたが、このあたりで本文は残り20ページほど。贋札をもらったバラモがその処分に悩む姿が描かれるわけでもなければ詩を書こうとするシーンもない。かといって物語はスムースに流れていくわけではなく、ときに大胆に転調し、語り手の考えが挿入されたりして戸惑わされる。例えば、バラモは贋札をどうしたらいいのかという点については、「最初に彼が思いついた方策は無邪気、あるいは無知を装うこと、つまり、札がおかしいとはまったく気づかなかったように振る舞い、本物であればしていたように、毎月給料をもらっていたときと同じように交換すること」と言って、バラモの考える解決策を探っていくが、「こうした問題がなかったとしても、どうやって無邪気を装うかという、もう一つ、それ以前の問題があった。それは克服できない上に、計り知れないものでもあった。その考えは自然らしさを真似る、つまり、臨機応変に即興でするということ。そしてこれは世界一簡単なこと、簡単さの見本のように思えるが、実際は何よりも難しいことであり、自然であろうとするもくろみ自体、矛盾すること、自滅的なことだった。彼の場合、失敗することがあらかじめ運命づけられていた。なぜなら自分の行動の流れを即興で作っていこうとするなら、まるで本当に即興でしているかのように行動しなくてはならなかったし、また、同時に、本当に即興でしていたかもしれないからだ」等々、バラモが考えなさそうなことまで口にした挙句、「小説の体裁になってはいるが、これは文学史の本である。フィクションではない。なぜなら主人公は存在したし、彼はイスパノアメリカのアヴァンギャルドの一大転機となる瞬間として研究され続けている有名な詩の作者であるからだ。そうであるなら、読者は、これまでどうしてフィクションや歴史的事実のフィクション化(本書の場合には当てはまらない)で習慣的に用いられる〈自由間接話法〉という方法で主人公の考えを表してこられたのだろうと疑問に思ったかもしれない」と言って、自分が『バラモ』を書くにあたり「主人公の内的であり、同時に外的でもある視点を創りだす」自由間接話法を用いているわけを説明し始め、文学について、また、バラモの『幼子賛歌』という作品とアヴァンギャルドについて、そして金と自由間接話法の一致点について長々と論じたりする。するとまた疑問がわく。バラモに対する「文学史の本」を書いているのであれば、「バラモ」という詩人の項目、あるいはモノグラフのはずだが、それにもかかわらず、彼の生年も経歴もはっきり記されない。おまけに、母親は広東語を話す偏執症の中国人として突如登場したりする。語り手は、自ら述べるように、本当に「文学史の本」を書いているのだろうか、それとも、「文学史」をだしにしてフィクションを書いているのだろうか。
とりあえずそんな疑問も棚上げして、話を戻そう。残りわずか20ページしかないのに、いったいどうやってバラモに200ペソの贋札を処分させ、20世紀中央アメリカを代表する詩を書かせるのか。最初に呈示されるこの問いに読書の焦点はいっそうしぼられるのだが、この2つの問いの解決は、なるほどこういう手があったのかと呆気にとられる。先の粗筋に出てきたものや場面をうまく再利用して、それまで帰結に向けて綱渡りのように見えた筋立てを、物語全体を破綻させることなく、緻密に計算されたかのような筋立てに変えてしまうからだ。そのうまさこそがアイラを読み続けたくなる主たる要因なのだろう。
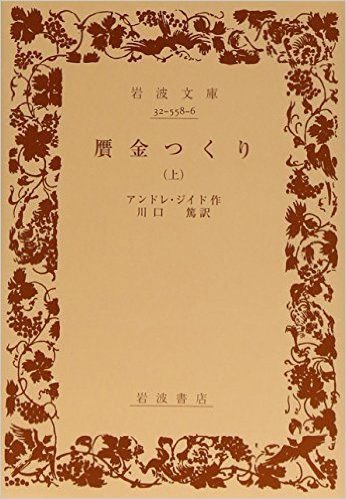
『贋金つくり』
アンドレ・ジッド 著/川口篤 訳
版元の岩波書店さんによる紹介はこちらへ
ところで「偽造という手段は現代小説にあまりにも多く見うけられ」と断られなくても、作品冒頭で「贋札」という言葉が出てきたとたん、ジッドの『贋札つくり(あるいは、贋札つかい)』を連想する読者もいるのではないか。ジッドは登場人物の一人である作家エドゥワールに「贋札つくり」という作品を書かせようとする。そのエドゥワールが構想し、書きだす作品が、実はジッドの『贋札つくり』であればわかりやすいのだが、タイトルにされている「贋金つくり」は物語にあまり絡んでこず、作品そのものは、エドゥワールが日記の中で小説について考察するように、小説の新たな書き方をめざすものとなっている。しかし、そのエドゥワールは自身の作品を説明するにあたって、「贋の十フラン金貨を想像して下さい。実際には、それは二スーの値打ちしかない。が、贋だと気づかない限り、十フランの値打ちがあるでしょう」(川口篤訳、岩波文庫)と言う。円を例にすれば、1万円札の原価は22円ほど、そして1円硬貨は3円くらいらしい。ただ、造幣局のホームページでは、「貨幣の製造原価(コスト)については、国民の貨幣に対する信用を維持するためや、貨幣の偽造を助長するおそれがあることから、公表していません」とあるが、紙幣を製造している国立印刷局のホームページにはこうした説明はない。それでも「日本の通貨そのものに対する信用や信頼」という言葉がある。物としての1万円札そのものは小さすぎてほとんど役に立たない。本の栞にするには大きすぎるし、障子や襖の破れ目に貼るには不細工、メモにするには余白が少なく、折り紙にすれば、さて何が作れるか。それでも、原価がわずか22円ほどらしいその紙は何かと交換するときに1万円分の役割を果たす。とはいえ、社会情勢が変われば、紙クズ同然になる可能性もある。アイラは『バラモ』で、「金は抽象であり、またその有用性はそこにしかない」と語り手に言わせる。信用・信頼という具体性のないもの、1つの抽象が現在の世界を支配し、人間社会に多大な影響を与えているのだが、この関係は、フィクションとリアリティを考える1つのヒントになるのではないか。
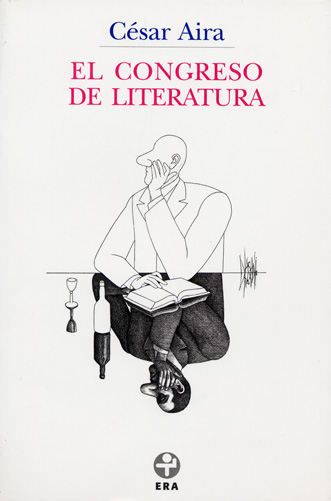
『文学会議』原書
El Congreso De Literatura
(Ediciones Era, 1997)
この『バラモ』を出版した年の6月にアイラはスペインの『エル・パイス』新聞のインタビューを受けている。アイラはどんな作家か、その一面を知るためにそこでの発言をまとめながら、少し紹介してみたい。ちなみに1975年の処女作『モレイラ』以後、現在(2015年)までに、アイラは90作あまりの本を出している。
――多作家ですね。1998年には7冊の本を発表しておられます。
リストでは多く見えますが、とっても薄い本です。わたしはほとんど書かない、というのも、書くこと以外何もせずに何年も過ごしていますが、日に30分以上書けたためしがない。たくさん書いてると言われると、頭の中で翻訳し、とてもうまく書いてると言われているかのように聞きます。量に関しては、誰でも日に1ページ、2ページ、あるいは決心すれば10ページ書けます。大切なのは書いてるものが出版できるということ。わたしは日にわずかなページしか書きません。そして3カ月すれば100ページ書いてることになり、それが1冊の本となり、出版される。そして1年後には3、4冊書いてる。10年前から100ページを超えたことはありません。
――本を書き始めるたび、その本が独創的なものである必要性、考えにとりつかれますか?
ええ、わたし以前にはなかったものを世界に残すということが、わたしに割り当てられた唯一の役目です。それが芸術家、作家の最も真正な役目だと思います。ときどき、2つの意図、新しいものを作る、そして良いものを作るという2つの意図が衝突します。その2つから選ばなければならないのであれば、良いものより新しいものであってほしい。
(略)
――あなたの小説は不条理なこと、シュルレアリスティックなことが歴史的要素といつも結びついてます。
本来の意味での歴史とはおそらく違います。歴史小説と呼ばれるものをたいてい避けてますから。でも確かに現実の出来事を頼りにしています。わたしは日記みたいに自分の小説を書いています。1ページずつ即興で作り、経験した出来事、閃いたことを入れていきます。そう、そうしたことをプロットに混ぜていくだけで不条理な調子になるんでしょうね。
――それぞれの小説が完全な即興なのでしょうか?
いいえ、たいてい、基本的な構想を考え、そこから即興で書くことができます。
――同時に複数の小説に取り組まれますか?
ときどき中断しますが、それは、書かなくてはならないとても切迫したものが思い浮かぶからです。でもそれはいい考えじゃありません。いちばんいいのは1冊1冊書くことです。
――インスピレーションを得るのに何を源泉にしておられますか?
本からだと思います。作家の90パーセントは、仮面を外して本当のことを言うなら、インスピレーションの大きな源は本だということを受け入れなくてはなりません。たいてい、経験だ、人生だと言いがちなんですが……。
(略)
――ご自分の作品に満足しておられませんか?
全然。いいものを読みたい人は、バルザック、ディケンズ、セルバンテスをお読みください。とるに足らない人間の本を読む理由がありますか?
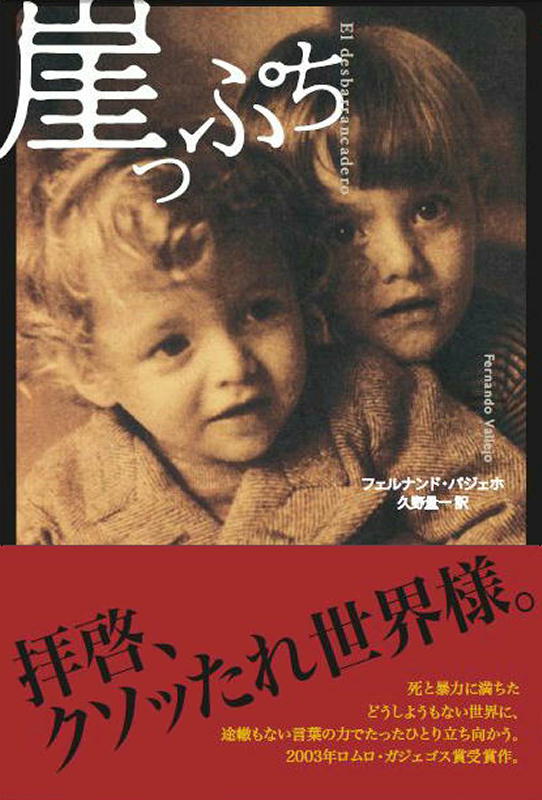
『崖っぷち』
フェルナンド・バジェホ 著/久野量一 訳
松籟社刊、紹介ページはこちらへ
インスピレーションの源は本であると断言し、書くのをやめたら読書すると言うアイラは、『ラテンアメリカ作家事典』(2001)を1人で書き上げるほどの読書家でもあり、ガルシア=マルケスやバルガス=リョサはよく読んでるものの興味はない、と言い、「本当に良い作家はもういなくなったといつも思っています。でも、びっくりすることもあります。わたしには天才に思えるのですが、コロンビア人のフェルナンド・バジェホを、そして少し前のことですがアドルフォ・コウベを発見したりすると。計り知れない驚きです」
そしてスペイン語圏の文学を総括して、「20世紀のスペイン語の最も偉大な作家はレサマ=リマとボルへスの2人だったと思います。2人は完全に識別できるスタイルをそなえていますが、それは違う理由によるものです。レサマ=リマはバロック、とりわけ文体上の構造によって。ボルへスは引き算、ほぼ中性の簡潔さによって。それが完璧に識別できる天賦の才能のおかげで彼を作ってもいます」
ではアイラのスタイルとはどのようなものなのだろうか。自分にはスタイルがない、と言うアイラだが、先に出した「即興」という言葉がキーになるかもしれない。だからこそどれだけ書いても作品がパターン化しないのであり、その即興の妙がアイラを読む愉しみの1つとも言える。『バラモ』という作品でも、例えばバラモVáramoという名をアルファベットのVだけで表せば、バラモも、また彼の置かれている状況も十分にカフカ的なものとなるし、作者はセサル・アイラでなくてもよくなる。
どれか1冊を読んで、これがアイラなどと判断を下すことは不可能。何冊か読んで、こういうことをするのがアイラか、とかろうじて言えるかもしれない。だからこそまたぞろ読むのだが、いつであれ本の薄さをなめてかかると、ひどい目にあう。どこに連れて行かれるのかわからないからだ。目の離せない作家と目される理由はそこにある。
(2015.10.3)
|

