2018/4/26−11/8
『ボマルツォ』への旅
かつて、イタリア・ルネッサンス期に名門オルシーニ家に生まれ、やがて「聖なる森Sacro Bosco」を創るボマルツォ公、ピエル・フランチェスコ(通称ヴィチーノ)の生涯を描いた小説Bomarzo(『ボマルツォ』)の翻訳『ボマルツォ公の回想』(集英社、1984)を共訳した(左下の写真がそのとき用いた1981年のSudamericana版)。
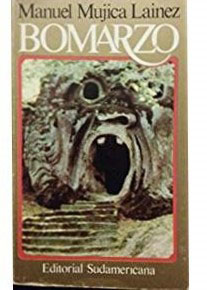
Bomarzo
『ボマルツォ公の回想』原書
Sudamericana版
そして、ベンヴェヌート・チェッリーニ、ミケランジェロ、カール五世、パラケルスス等々名立たる人物や歴史的事件を巧みに絡み合わせた、日本語にして2段組み600ページというこの大部な小説をもとに、「既視のボマルツォ」という文を『ユリイカ』(1995年2月号、拙書『現代ラテンアメリカ文学併走』所収)に載せた。ただ、翻訳をしているときも拙文を書くときも、不明だったことがあった。図書館にある大型の地図でボマルツォの位置を調べるような当時からすればPCが普及した今はまるで夢のような世界であり、インターネットのおかげで、『ボマルツォ』の舞台となる地を鮮明な画像で見ることも、その地をめぐる情報もたくさん入手できる。それでもなお、解決できないような謎は残るもので、ずっと気になっていた。
ところが昨年、原稿依頼を受けて、どうするか悩んでいたとき、ふと閃めいたことがあり、そのまったくの思いつきを形にすれば、その気がかりも解消するのでは、と甘い期待を寄せた。
メンフィスも過去の世界のいかなる奇観も
聖なる森には道を譲る
この森は唯一無二 模倣もかなわず
「唯一無二 模倣もかなわず」と『ボマルツォ』の主人公ヴィチーノが大見得を切る「聖なる森」の全容はどのようなものか。『ボマルツォ』では主人公の心の動きを示すためにその森に造られたニンフや象、ドラゴン、亀、巨人等々、20あまりの像や建造物について言及されている。今では「聖なる森」は「怪物公園Parco dei Mostri」となり、森を特徴づけるそうした奇矯な像や建造物の画像はネットで検索すれば即座に、大量に見られるのだが、あくまでも二次元。180度の絵画と違って、彫像は360度。裏側があるのだ。なかでも翻訳していたときからずっと気になっていたのが、物語で最も重要な役割を果たす「魔王の像」あるいは「地獄の口」の内部。残念ながら、その内部はネットでも把握できない。そこで、この4月下旬から5月初めにかけて、ようやくのことでイタリアを訪ねることにした。
4月26日、ローマのテルミニ駅の改札を抜け、ローカルだから差別されているのかと思われるくらい遠くにあるホームで、9:00発フィレンツェ行の普通列車に乗る。珍しいことなのかもしれないがほぼ時間通り出発した列車の窓から、ローマ郊外や田園風景、ときおり町の建物を見ながら、9:52頃、アッティリャーノ=ボマルツォ駅に到着。日本のように騒がしいアナウンスのない静かなホームに降り立ち、まわりを見ると、反対側はローマに向かうホーム、そしてその向こうは引き込み線、彼方は林か森か。列車が出て行くと、ただ静寂。改札を出ると、あたりはまるで眠りつづけているようで、駅前には車が何台か駐車しているものの、タクシーは停まっていない。バスが待っているわけでもない。また駅に沿って延びているものの、行き交う車もない対向2車線の通りの向こう側にも、カフェやレストラン、商店といったものはなく、戸建ての住宅や複数階の建物がぽつぽつとあるだけの閑散とした風景。日本で調べたとおり、観光地に連絡する駅前のありようではなく、ここから怪物公園に向かうのは大変そう。それでもこの駅で降りた。旅行業者が組んでいるローマからの日帰りツアーは天空の街チヴィタや城郭都市オルヴィエートといった、より観光地らしいところに行くついでに立ち寄るみたいなものばかりで、ボマルツォ滞在が1時間、それも怪物公園だけで城には行かないからだ。そこで、ゆっくり森と城を見る時間をとるために個人でも行けるツアーを調べ、オルヴィエートを拠点にするウンブリア・イン・ツアーUmbria in Tourというのを見つけた。
駅前には、その会社を運営するルチアンナ・コッポラLucianna Coppolaさんが迎えに来ていた。彼女の運転する車に乗って、町を外れ、野や畑や木々、石垣を見ながらぼうっとしていると、10分ほどで怪物公園の前にある駐車場に着く。城にも向かうため、1時間半後に回収してもらうということにして別れ、切符売り場でチケットを買う。€10。代わりにもらったイタリア語の案内図を手に、コンクリートの道を進み、城壁のような門をくぐる。

「聖なる森」(現「怪物公園Parco dei Mostri」)案内図
そして順路に従って、舗装された道や板石を敷いた道、砂利道、土の道を歩きながら、雑木林というより森の中を、平地や丘陵、小川の辺に置かれた38の像や建造物を眺めていく(帰りに念のために英語の案内図をもらったが、なぜが、途中の順路が違っていたり、像や建造物が3つ少なく35になっていたり、説明が違っていたりする)。順路となっている道は、小川に降りるとき以外は上り坂で、上り詰めたところにはヴィニョーラ寺院Tempio del Vignolaが建っている。
1938年、サルバドール・ダリはこの「聖なる森」を訪れ、自らフィルムに収まった。その様子の一部はYouTubeで「Salvador Dali al parco dei mostri di Bomarzo」と検索すれば見られるが、そのときの滞在が「聖アントニウスの誘惑」(1946)のインスピレーションを与えたとも言われている。その後、1949年、ミケランジェロ・アントニオーニが10分の短篇を撮り、「1950, La Villa dei Mostri」としてまとめる。これもYouTubeで見られる。また同年10月に、マリオ・プラーツが訪問し、「ボマルツォの怪物」というエッセイを書く(『官能の庭』所収、ありな書房)。そして、ヴィチーノ・オルシーニの死後、自然のなすがままにされた森は、1954年、イタリア人ジョヴァンニ・ベッティーニの所有となって、整備が開始され、400年の眠りから覚め始めるのだが、この年、マンディアルグはボマルツォを訪れ、1957年に『ボマルツォの怪物』を出す。マンディアルグは現在の道順とは逆に最上部にあるヴィニョーラ寺院から下に歩を進めている。彼の本に載る写真は撮影されたのが整備開始前とも開始直後とも判断がつかない。いずれにしても、廃園にたたずむ彫像群といった趣を醸しだしているが、今、その白黒写真のような写真を撮るのは不可能。一方、この本を翻訳した澁澤龍彦は「ボマルツォの「聖なる森」」(『幻想の画廊から』所収、美術出版社、1967)というエッセイを書くが、1970年に実際に訪れて「バロック抄 ボマルツォの怪物」(『ヨーロッパの乳房』所収、立風書房、1973)で書き直したり、補足したりしている。

「魔王の像」外観
マヌエル・ムヒカ=ライネスは1958年7月13日に初めて森を訪れたが、以前にも来たことがあるような既視感にとらわれる。当時は生年すらはっきりしないほど資料が乏しかったボマルツォ公だが、できうる限りの資料を集めて、聖なる森の意味を探るために彼の一生を書きはじめ、1959年8月2日には再訪して城も見て回り、1962年、70パーセントが想像という『ボマルツォ』を発表する。その『ボマルツォ』に導かれて、ムヒカ=ライネスが「岩はそれぞれその構造の中に一つの謎を閉じこめており、その謎の一つ一つが私の過去、そして私の性格の一つの秘密であった。その謎を発見せねばならなかった。本質的な姿を覆っている表皮をどの岩からも引き剥がさねばならなかった」と主人公ヴィチーノが言う岩がどのようなものかをゆっくり眺めていくと、校外学習なのか、後から来た元気な小学生の一団に追い抜かれたり、わずかばかりの見物客たちに先を越されたりする。そして、やがて、ボマルツォに来た最大の目的である20番目のOrco(冥界の神オルクス。人食い鬼)の前に来る。英語版では19番目で Ogre「人食い鬼」。この像を目にして、マンディアルグは「人食い鬼だと言われている巨大な人間の首」、澁澤は「魁偉な人間の首」、そしてムヒカ=ライネスはヴィチーノが鏡で見た「魔王の像」と捉える。
マンディアルグはその像について、「しかめ面を見せているこの人間の首のまわりに、茨や灌木は蓬々と生い茂り、まるでこの顔の芝居じみた恐ろしい髯のようになっている。この首は、地面すれすれに置かれていて、傾いて立っている小さな家よりも容積が大きいのである。その口は何でも呑み込んでやるぞと言わんばかりの大きさで、あんぐり開かれているので、諸君はちょっと頭を低くするだけで、怖ろしい歯のあいだをくぐり抜けて、その中に入ることもできるほどである。口のなかは、ちょうど舌のあるべき場所に、自然の岩を彫り込んだ一脚のテーブルと腰掛があり、諸君はそこに腰をおろして休むこともできる(澁澤訳)」と『ボマルツォの怪物』で記している。

「魔王の像」の口の中。
石のテーブルが据えられている。
一方、澁澤は、「この「聖なる森」のなかでもっとも奇怪なアイディアの像がある。/それは、ぽっかり口をあけた、魁偉な人間の首である。地面から首だけ突き出して、絶叫している恐ろしい地獄の魔王の顔のようである。この顔の口は、直径二メートルを超えるから、優に人間が立って通れるだけの大きさを有し、一種のグロッタになっている顔の内部には、石を刻んだテーブル(同時に舌に見立ててある)が備えつけてある。かつて、オルシニ候に庭を案内された客人が、ここで、しばしの疲れを休め歓談したものと想像される。グロッタの内部で笑い声でも立てれば、その声は大きく反響して、口から外へ飛び出し、あたかも地獄の魔王が哄笑しているようにも聞えたことであろう。何という奇想天外なアイデアであろう」と表現している。
マンディアルグの『ボマルツォの怪物』、あるいは澁澤の『ヨーロッパの乳房』に載る写真は白黒である。その写真で見ると、マンディアルグが説明するように首のまわりに「茨や灌木は蓬々と生い茂り、まるでこの顔の芝居じみた恐ろしい髯のようになって」おり、おどろおどろしさを醸し出してさえいる。ところが、現在では、まわりの「茨や灌木」が刈り取られて、ちょうど髯を整えたあとの顔のようにさっぱりしている一方、そのときにはなかった木が首の左下から斜めにのびて左目にかかっている。枝のように細い木だが、それが顔を押さえつけているようにも見え、最初目にしたときには、この「巨大な人間の首」の表情はなんだか滑稽にも思えた。口は確かにこれ以上ないくらい大きく開かれているが、それは「何でも呑み込んでやる」ためか、「哄笑」するためか。つまり、何かを吸いこんでいるのか、あるいは吐き出しているのか。
いずれにせよ、大きく開かれたその口の周り、というより唇に当たる部分にはOGNI PENSIERO VOLA「すべての思いが飛ぶ」という言葉が刻まれている。ただこの言葉はオリジナルとは違うらしい。ジョヴァンニ・ゲッラが1598年にこの像を模写したものでは、LASCIATE OGNI PENSIERO VOI CH’ENTRATE「汝ら、中に入る者、すべての思いを捨てよ」と彫られたことになっている。『ボマルツォ』でもそれを踏襲しているのだが、むろんこれはダンテの有名な言葉、『神曲』の「地獄の門」に書かれたLASCIATE OGNI SPERANZA VOI CH’ENTRATE(汝ら、中に入る者、すべての望みを捨てよ)の一語、「希望SPERANZA」を「思いPENSIERO」に変えたものである。ただ、換えられた言葉「希望」は未来を志向するが、「思い」の向かう先はそうした時間の制約を受けない。「思い」はどこにでも飛んでいくものであり、人は生きている限り、様々な思いにとらわれ、悩まされる。それをすべて捨てること、心を無にすることは凡人にはできない。このような文を書いているときでさえ、情けないことに、あらぬことを考えたりする。「すべての思いを捨てよ」という言い方はいざ中に入ろうとする者の意志の強さや決意のほどを問うようにも感じさせられるが、最後にこの口に入ろうとするヴィチーノでさえ、「エトルリアの羊飼いたちのようにハープを弾き、歌うあの少年の声」だけは耳から消すことができない。

「魔王の像」内部より。
目の部分から外光が差し込む。

口の陰が不気味なシルエットを形作る。
中に入るまえに像を外から見ると、口の中は暗い。とりあえず九段の低い階段を上り、分厚い下唇を越えて中に入る。するとマンディアルグや澁澤の言葉どおり。小さな矩形の部屋のようになっており、真ん中には前方(入口)に向かってのびる舌のような感じでしつらえられた、角を丸めた四角いテーブルがある。そしてそのテーブルを取り囲むように、三方の壁に沿って、それぞれ五、六人がいっしょに腰をおろせるくらいの長いベンチがしつらえられている。テーブルを前にしてその狭いベンチに坐ると、閉所にいるような圧迫感はなく、むしろ気分が落ち着く。視線を上げると、鼻の穴は内側まで貫通していず、光は天井のすぐ下にある目から入り込んでくるだけ。だが部屋の中はその上部からの光があふれて明るい、というわけではなく、全体とすれば、むしろ薄暗い。入口、つまり口に当たる部分から外を見ると、外の光がまぶしい。ちょうど逆光で、何の調節もしないで撮った写真に近い感じに、口の陰が強調されて不気味なシルエットが浮かび上がる。視線の位置で変化するこうした明暗が一つの暗示となるのかもしれない。つまり、この像は現世と黄泉の国の境を示すためにあるという。だから口の中に入る者は心しなければならない。もしかしたら元に、現世に戻れないのだと。この空間は、やはり、森を歩いて疲れをとるために、あるいは人をもてなすためにあるものではないように思える。
日中でもそんなふうに感じさせる空間だが、夜間訪れたらどんな感じだろう。『ボマルツォ』の時代の照明は主に蝋燭やランタン、あるいは松明のはず。そんな頼りない光を頼りに城を降り、森の中を目的地まで進むのは、たとえ月が出ていたとしても容易なことではないし、なにより恐怖にとらわれるだろう。ただ、ヴィチーノは家臣が設えたおびただしい篝火、とはいえ「糸杉を隠すような煙っぽい篝火」に導かれて「魔王の像」の前まで来る。木々に囲まれたその像は、篝火の揺らめく光を受けてどんなふうに見えるのか。はっきりした周りの明暗、そして揺れる光の作用で息づいているような気にさせられそう。ムヒカ=ライネスは物語の最後でこの魔王の口の中に、庵として岩をえぐらせた空間に入るヴィチーノを次のように描いた。「その中に入るときには拳を握りしめたが、不安を抱くどころか類まれな幸福感を味わった。精神分析医であれば、それは私がその薄暗がりの中で、母胎内での幸福感を、私が思い出しえない母親の避難所を、あるいは私の祖母、素晴らしい女性であるディアナ・オルシーニの膝の庇護をふたたび見出したことに起因するものと説明するかもしれない。青銅の扉がその奇怪な顔面像の口を閉じるようについていたが、私はその扉を閉めた。(中略)部屋の中央にはまるで棺台のような、端の丸められたテーブルがあったが、その周りを壁にそって石の長い椅子が囲んでいた。(中略)大きな蝋燭が一本、テーブルの上で明滅している。私はその横に杯を置いた。マントを脱ぎ、冠を外して長椅子に腰をおろした。炎の揺れがざらつく壁の肌に私の背中のこぶの形を動かしていた。まるで悪魔の喉にいるかのごとく洞窟の中心にいて、扉を開け、私の隠遁所から月の夜を眺めた。鍾乳石のような大きな二本の牙の下、口の空洞の中に森の影がくっきり浮かび上がっていた。そして、目の穴の向こうにはくすんだ銀の空が輝いていた」
このあと『ボマルツォ』は最大のクライマックスを迎える。ヴィチーノがテーブルに置いた杯を満たしている乳状の液体(不死の薬)を飲むことになる。だが、皮肉なことに、その杯には毒が盛られている。結局、ヴィチーノはそうして毒殺されるのだが、それでも不死の生を得て、数世紀のちに、別の人間の肉体を借りて自らの生涯を回顧し、『ボマルツォ』という長い物語を語ることになる。誰かの記憶にとどまっているうちは、あるいは思い出される限り、人は不死の存在であり続けるからだ。
この悪魔の首の他、聖なる森にはグロテスクな像、暴力的な像、マンディアルグや澁澤が指摘したようなエロチックな雰囲気を醸しだすような像がいくつもある(が、そうしたものについては稿を改めたい)。しかし、1552年に造園を開始したとされるこの森はヴィチーノの死後、遺族に顧みられない。おまけに、1645年にマルツィオ・オルシーニがランテ家に所領を売り渡してしまう。そして20世紀になって、ダリやアントニオーニのおかげで注目され、また1954年にジョヴァンニ・ベッティーニが地所を買い、いくつかの像を修復したり、道を創ったりするなど整備をして、2年後の1956年に「怪物公園」として公開することで人目に触れるようになった。ただ修復作業は今なお続いており、冬季には調査、補修作業を行っている、とジョヴァンニの孫のフェデリーカ・ベッティーニFederica Bettiniさんは言う。
ダリやアントニオーニ、マリオ・プラーツは、おそらくマンディアルグも、整備前に訪れ、400年という歳月にむしばまれ、荒廃した森を見たことになる。だが、1958年に訪れたムヒカ=ライネスはある程度整備された森を目撃したわけであり、どれほどの整備状態だったかはわからないが、そのときには、ヴィチーノが作ったときの像のありように似ていたのではないか。岩が苔むしておらず、白っぽい岩肌がそのまま見え、陽に当たれば輝き、目にまぶしかったかもしれない。

城から見下ろすボマルツォの街並み
順路に従って最も高いところにある寺院まで行くと、約束の時間が近づいている。その他の気になる像を見直すということもできず、急いで駐車場に戻ってルチアンナさんと合流し、小高い丘の上にあるオルシーニ城へ向かう。坂を上って数分、城の下の駐車場に車を入れて、城に続く坂を上がる。週日は城には誰も入れないとのことだったが、ルチアンナさんがコムーネの長(人口が1600人くらいなので、人口で市町村と呼び名を変える日本に言い方に従えば、村長)であるイーヴォ・チャルデアIvo Ciardea氏と交渉して、内部を見せてもらえることになっていた。聞けば、わたしが『ボマルツォ』の訳者であったことが幸いしたらしい。そのチャルデア氏が自ら中を案内してくれた。窓を開け放ってくれたおかげで、聖なる森を含めて遠くまでボマルツォの周囲の風景が俯瞰できたし、室内の天井画や壁面のフレスコ画、そしてガラスケースに入ったミイラも、またテラスに出れば、城を起点にして丘の上に細長くのびるボマルツォの街並みが間近に見えた。翻訳している段階では、城の大きさや構造、周りの状況がよく分からず、なんとなく想像して城を組み立てていたが、そうして目の当たりにしてみると、想像した小説の舞台と実際の風景に違いに驚く。まさしく百聞は一見に如かず。ただ、それでも、すっかり納得できたわけではなく、先に目にした彫像群の意味は解けない。考えながら見て歩くには1時間半では足りず、もう一度たっぷり時間をかけてじっくり見るしかない。それにしても『ボマルツォ』の中で、一つひとつ、像を意味づけていったムヒカ=ライネスの想像力にはやはり脱帽するしかない。
*
旅は思わぬ出会いをもたらしてくれる。帰国した翌日、5月4日の朝、NHKのBSで「プレミアムカフェ 男自転車ふたり旅 イタリア」(初回放送2009年)という番組を見ていると、最後のほうでオルヴィエートの町が映され、蟹江一平と猪野学がそこで小さな女の子を乗せたバギーを押す夫婦に出会うシーンがあった。男性はコメディア・デラルテの俳優アンドレア・ブルニェーラAndrea Brugnera、そして横にいる女性の下には「奈津子」という文字。もしかしたらと思い、Umbria in Tourで日本語の予約、問い合わせを担当している富奈津子Tomi Natsukoさんにメールで訊いてみた。するとまさしく本人。富さんにはボマルツォに行くにあたってひとかたならずお世話になり、メールを通して、鉄道やストライキの情報を含めてイタリア旅行の注意事項を丁寧にお教えいただいた。また、この夏、神戸に帰省されたときにはお会いして歓談することができたが、この拙文を書いているときには不明な点を調べてくださり、その過程でフェデリーカ・ベッティーニさんという存在につながって、怪物公園の開園年がようやく判明した。この場を借りて富さんに、そしてまたルチアンナ・コッポラさんに深く感謝したい。
(2018.4.26−11.8)
|

